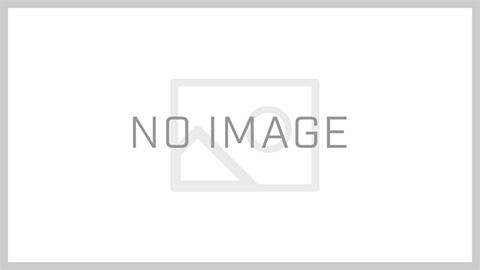これぞKeyです。
理屈じゃどうにも説明できないんだけど、なんだかやたら感動してしまう。今回も見事にやられました。「野球がしたいです」で大洪水不可避。不思議な充実感を覚えさせてくれます。
その中で説明できそうなところをピックアップして書きました。ここまでストーリーのスケールを大きくした理由とは、一体なんでしょうか。
スケールの大きな展開の理由
テヴアという一国が崩壊しかける状況にまで陥るという、ギャルゲー学園モノにしてはやたらスケールの大きな展開になりました。数年前にゲームをプレイしていたときは違和感を覚えたのですが、こうしてアニメで観ると、ストーリーの演出としてきちんと効果が出ていることがわかります。
すなわち、日常と非日常の対比です。平和な学校と、戦争状態の国。みんなでいるリトルバスターズの面々と、たったひとりのクド。まったく異なるふたつの状況を描いています。
唐突に現れた非日常がその存在をどんどん大きくしていき、日常の世界からそこに一人、クドが向かいます。物理的な距離も周囲の状況も、普段とは程遠いところに、彼女は立ったのです。
ではなぜここまでスケールを広げて、日常と非日常を描いたのか。
非日常と仲間
「リトルバスターズ!」には、「仲間」という一貫したテーマがあります。それを念頭に置いて見てみましょう。
恭介も最後に言っていましたが、日常の裏には必ず非日常が潜んでいます。ふたつは表裏一体。簡単に入れ替わってしまうものです。結果、自分の周囲の人が、あるいは自分が、ある日突然、非日常に行ってしまうのです。
今回、生半可なレベルではない、もう絶望するしかないほどどうしようもない状況として、ロケット打ち上げの失敗と母の危機、テヴアの紛争が描かれました。手に負えない、抗うことのできない非日常です。そこにクドが一人放り込まれてしまった。
でも、だからといって他人事にならないのがリトルバスターズです。
テヴアの状況、クドやその家族の安否は、当事者ですらどうなるかわからないのだから、周りの人間にはどうにもできるはずがありません。それでも、どうすることができない中でも、仲間として無事を祈る。存在を絶対に忘れない。「仲間」を描いてきた「リトルバスターズ!」が示す、またひとつの「仲間」の形なのです。
どんなに遠い非日常の世界にいても、仲間はつながっている。支え、背中を押してくれる。その表現としてあの部品ワープがあったのではないでしょうか。だとしたら、僕は心から納得ができます。
たまに「超展開」と揶揄したり、出来事すべてに理屈や描写を求める方もいらっしゃいますが、それは無くてもいいものだと思います。だってエンターテインメントですから。表現としての意味があればそれで十分です。どうやって部品がワープしたのかとか、どうやってクドは帰ってきたのかとか、そこを追求する意味はないと僕は思っています。
世界の歯車
人類より先に宇宙へ行き、その可能性を示したライカ犬・クドリャフカ。
クドの母はクドにその名前を授け、「世界の歯車になりなさい」と言いました。可能性ある未来へ向かって世界を「進める」ための歯車になってほしいという、母の願いです。
クドにとって、母の言う「世界の歯車」になるのは、まだ夢の途中。しかし彼女は、誰かの仲間としてなくてはならない、かけがえのない存在として、クドはリトルバスターズの歯車となっています。
人とつながり、みんなで前に進む――母の言うものとはまた違う形で、クドは立派な世界の歯車になっているのです。